第1期石垣市障害児福祉計画
第1期石垣市障害児福祉計画
1) アンケートの実施概要
1 調査の対象者
調査の対象は、本市に在住する18歳未満の障害者手帳所持者等の189人が調査対象となっています。
2 調査対象地域
石垣市全域
3 調査の期間
平成29年11月上旬~平成29年11月末日
4 調査票配布回収方法
対象者に対し、郵送による配布・回収を実施しました。サービス提供事業者や各種関係団体等によるご協力をいただきました。
5 調査票の回収状況
| 配布数 | 回収数 | 実質回収率 | |
|---|---|---|---|
| 調査票回収状況 | 189 | 76 | 40.20% |
2) 調査結果の概要
1 対象者の性別・年齢・ご家族等・障がいの状況について
問1 性別・年齢(平成29年11月1日現在)について
調査対象者の性別は、「男性」が63.2%「女性」が36.8%となっており、男性が26.4ポイント上回る状況にあります。
調査対象者の年齢層は、「6~11歳(小学生相当)」が30.3%で最も高くなっています。
次いで「12~14歳(中学生相当)」の27.6%、「15~17歳(高校生相当)」の26.3%、「0~5歳(未就学児)」の15.8%と続いています。
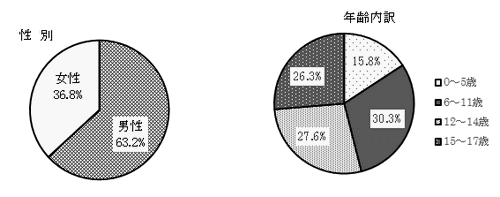
問2 同居家族
一緒に暮らしている同居家族は「母親」が94.7%で第1位となっています。
第2位は「父親」の78.9%、第3位は「兄弟姉妹」の63.2%、第4位は「祖父母」の6.6%、第5位は「その他」の3.9%となっています。
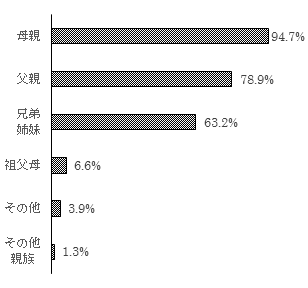
問3 所持している手帳と受けている診断名について
所持している手帳と受けている診断名は「療育手帳を持っている」が61.8%で最も高くなっています。
次いで「発達障害の診断を受けている」の30.3%、「身体障害者手帳を持っている」の21.1%、「これらの手帳は持ってなく、診断を受けていない」の9.2%、「精神障害者保健福祉手帳を持っている」及び「難病の診断を受けている」が同率の2.6%等と続いています。
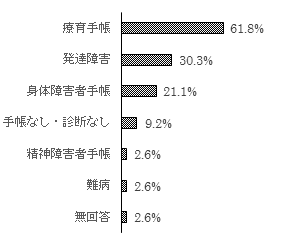
<手帳の等級や診断名について>
(1)身体障害者手帳
障害者手帳の所持者数は、16人となっています。
記載されている等級は「1級」が50.0%で最も高くなっています。
次いで「2級」の18.8%となっており、重度の等級である「1級」、「2級」の合計割合は68.8%となっています。
以下、「3級」の6.3%、「4級」の12.5%、「5級」の6.3%、「6級」の6.3%となっています。
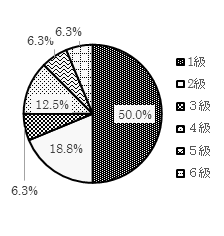
1)おもな障害の種類(限定質問)
障害者手帳に記載されている、おもな障害の種類は、「肢体不自由」が75.0%で最も高くなっています。次いで「内部障害」の18.8%となっています。
主たる障害は「肢体不自由(脳原性)」の8人が最も多く、次いで「内部障害(心臓)」の2人、「肢体不自由(下肢)」の1人、「内部障害(ぼうこう・直腸)」の1人となっています。
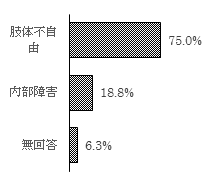
(2)療育手帳の判定
療育手帳の所持者は47人となっています。
記載されている等級は「B2」の55.3%、「B1」の23.4%、「A2」の19.1%、「A1」の2.1%となっています。
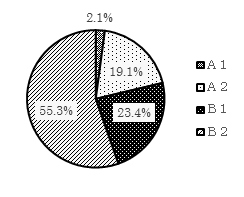
(3)精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障害者福祉手帳所持者は2人となっています。
記載されている等級は「2級」が1人、「3級」が1人となっています。
(4)発達障害診断の診断名
発達障害の診断を受けている者は、23人となっています。
診断名は「自閉症」が52.2%と最も高くなっています。
次いで「知的障害」及び「広汎性発達障害」が同率で13.0%等と続いています。
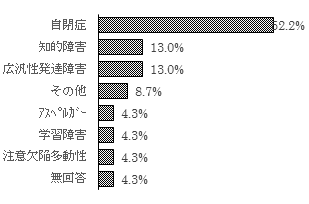
(5)難病の診断名
難病の診断を受けている者は2人となっています。
診断名は「ファロー四徴症」が1人、「ダウン症」1人となっています。
(6)手帳を持ってなく、診断も受けていないお子さんの心配なこと(限定質問)
手帳を持ってなく、診断も受けていない者は7人となっています。
心配なことは「ことばが遅れている」が71.4%と最も高くなっています。
次いで「不器用なところがある」の57.1%、「こだわりが強い」の42.9%等と続いています。
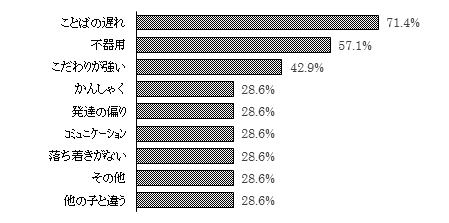
問4 現在受けている医療ケア
現在、何らかの医療ケアを受けている者は10人で13.2%となっています。
受けている医療ケアは、「服薬管理」が10.5%で最も高くなっています。
次いで「吸入」及び「吸引」が同率の3.9%、「経管栄養」「カテーテル留置」「その他」の1.3%と続いています。
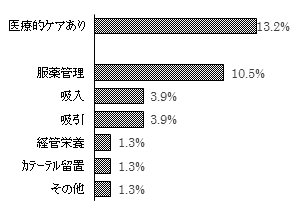
2 日常生活における介助や支援について
問5 日常生活で介助が必要なこと
日常生活で介助が必要かについては、「ひとりでできる」割合が最も高い動作は「室内の移動」で77.6%となっています。
次いで「食事」75.0%、「着替え」69.7%、「トイレ」64.5%、「入浴」53.9%等と続いています。一方、「見守りが必要」、「介助が必要」の割合が高い動作、項目は、「通院、通園・通学以外の外出」で64.5%となっています。次いで「通院、通園・通学」の53.9%、「家族以外の人とのコミュニケーション」の51.3%、「入浴」46.1%、「トイレ」の35.5%等と続いています。
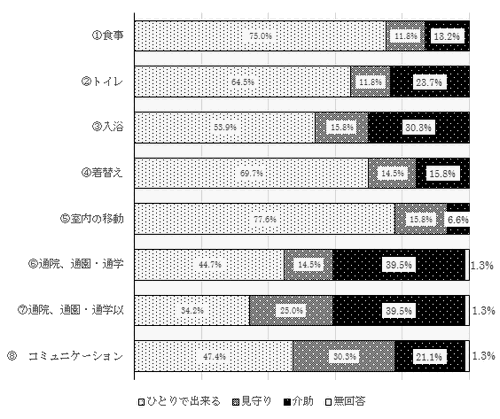
問6 主に介助をしている方(限定質問)
主に介助をしている方割合の第1位は「母親」の80.8%なっています。
第2位は「父親」の17.3%、第3位は「その他」の1.9%となっています。
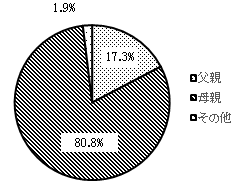
問7 介助者の悩みや不安について(限定質問)
介助者の悩みや不安について、「親亡き後の将来について不安がある」が73.1%と最も高くなっています。
次いで、「何かの時に介助を頼める人がいない」及び「何かの時に預けられる場所がない」が同率の36.5%、「自分の健康について不安がある」の34.6%、「長期的な外出が出来ない」の32.7%等となっています。
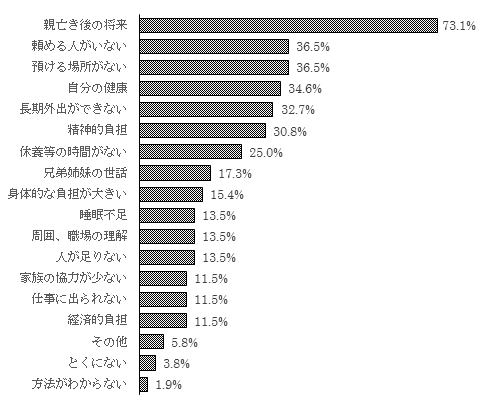
3 教育や保育について
問8 学齢について
「小学校入学前」が22.4%、「小学校入学後」が77.6%となっています。
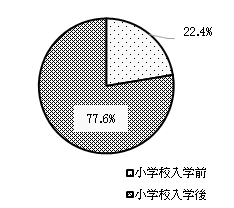
問9 日中の通園・通所について(限定質問)
日中の通園・通所については、「児童発達支援事業所」が100%と最も高くなっています。
次いで、「保育園・保育所」の35.3%、「幼稚園」の23.5%、「その他」の17.6%、「認定こども園」の11.8%、「子育て支援センター、子どもセンター」の5.9%となっています。
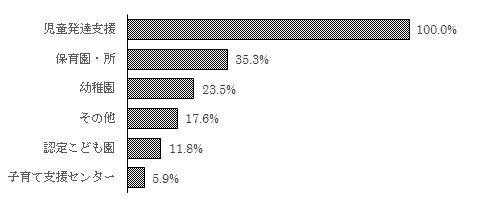
問10 通園生活等で、困っていることについて(限定質問)
困っていることについては、「周囲との子どもの関係が心配」が70.6%で最も高くなっています。
次いで、「子どもの将来に不安がある」及び「保育や教育・療育に関する情報が少ない」が同率の58.8%、「今後の進路について迷っている」の35.3%、「通園の送迎が大変」「職員の保育・指導の仕方が心配」及び「療育・リハビリテーションの機会が少ない」が同率の23.5%となっています。
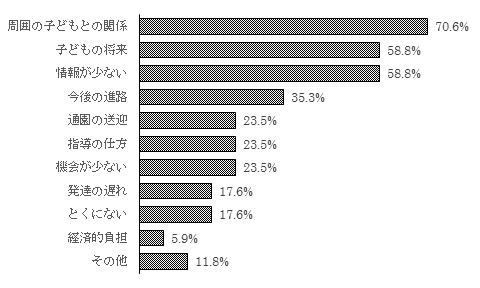
問11 通学している学校・学級(限定質問)
現在通学している学校・学級は、「特別支援学校(小・中・高等部)」が50.8%と最も高くなっています。
次いで、「普通学級と特別支援学級・情緒学級(小・中学校)」の23.7%、「普通学級のみ(小・中学校)」の11.9%、「高等学校・高等専門学校」の6.8%、「特別支援学級のみ(小・中学校)」の3.4%等と続いています。
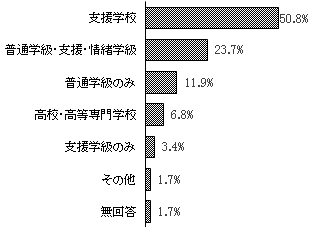
問12 学校以外の過ごす場所(限定質問)
学校以外の過ごす場所として、「放課後等デイサービス事業所」が66.1%と最も高くなっています。
次いで「とくに何も利用していない」の27.1%、「民間の習いごと・教室」の10.2%、「学童クラブ」の8.5%、「日中一時支援事業」及び「その他」が同率の5.1%等と続いています。
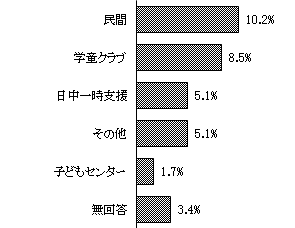
問13 学校生活等で困っていること、心配なこと
学校生活や今後の進路等で困っていることや心配していることは、「子どもの将来に不安がある」が67.8%と最も高くなっています。
次いで、「今後の進路について迷っている」の40.7%、「教育や療育に関する情報が少ない」の39.0%、「周囲の子どもとの関係が心配」の33.9%、「療育・リハビリテーションの機会が少ない」の27.1%等と続いています。
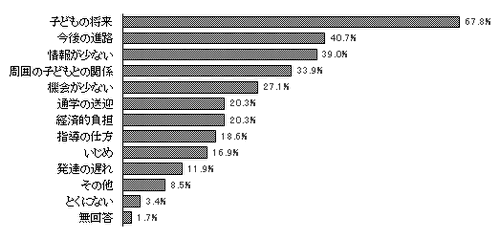
4 将来について
問14 将来の進学先
将来の進学先の第一位は「高等学校まで」の50.0%となっています。
第二位は「専門学校・高等専門学校・短期大学」及び「分からない」が同率の14.5%、第三位は「大学・大学院まで」の11.8%、第四位は「その他」の5.3%となっている。
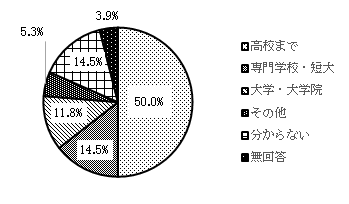
問15 将来の就職先
将来の就職先の第1位は「会社やお店などで働く(一般就労)」の39.5%となっています。
第2位は「地域の福祉就労支援事業所で働く」の25.0%、第3位は「分からない」の15.8%、第4位は「その他」の11.8%、第5位は「働くことは困難だと思う」の6.6%となっている。
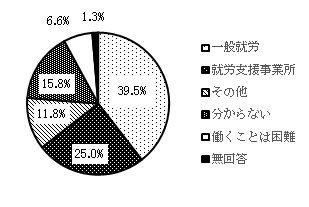
問16 将来の住まい
将来の住まいの第1位は、「ひとり暮らし、または本人の配偶者・子らと一緒に一戸建て、アパート、マンション」で40.8%となっています。
第2位は「親や兄弟姉妹などの家族と一緒に一戸建て、アパート、マンション」の32.9%、第3位は「分からない」の11.8%、第4位は「グループホーム」の7.9%、第5位は「入所施設」及び「その他」が同率の2.6%となっています。
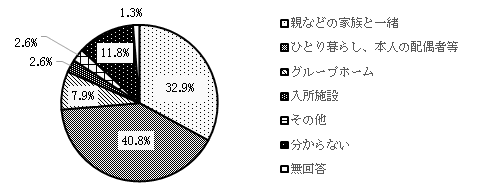
5 福祉サービス等の利用について
問17 サービスの認知度と利用状況について
A:主に18歳未満で利用できるサービス
サービスの認知度で、「知っている」という割合が最も高かったのは、「放課後等デイサービス」で92.1%となっています。次いで「児童発達支援」の82.9%、「医療型日中一時支援」の46.1%等と続いており、「知らない」という割合が最も高かったのは、「障害児入所支援(医療型)」の76.3%となっています。
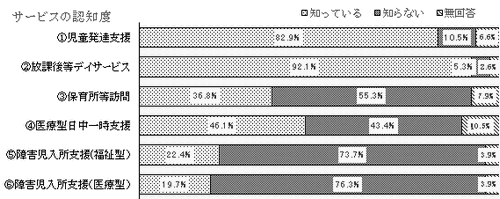
サービスの利用状況では、「利用している」という割合が最も高かったのは、「放課後等デイサービス」の47.4%となっています。次いで「児童発達支援」の22.4%、「保育所等訪問支援」の6.6%、「医療型日中一時支援」の3.9%となっています。
「利用したい」の割合が最も高かったのは、「放課後等デイサービス」の22.4%となっています。次いで「障害児入所支援(福祉型)」の19.7%、「障害児入所支援(医療型)」の10.5%等と続いています。
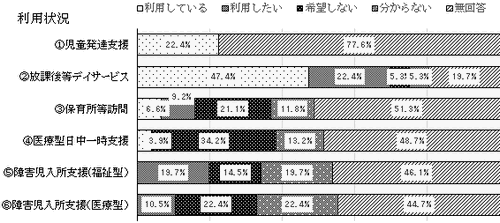
B:児童期~成人期にかけて利用できるサービス
サービスの認知度で、「知っている」という割合が最も高かったのは、「相談支援(計画相談)」で88.2%となっています。次いで「居宅介護(ホームヘルプ)」の68.4%、「日中一時支援」の60.5%等と続いています。
逆に「知らない」という割合が最も高かったのは、「同行援護」の65.8%となっています。
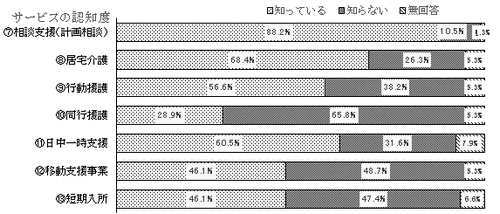
サービスの利用状況では、「利用している」という割合が最も高かったのは、「相談支援(計画相談)」の56.6%となっています。次いで「日中一時支援事業」の22.4%、「移動支援事業」の9.2%等と続いています。
「利用したい」の割合が最も高かったのは、「移動支援事業」の18.4%となっています。次いで「日中一時支援事業」の15.8%、「行動援護」の13.2%等と続いています。
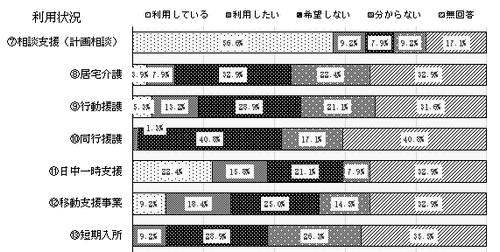
C:18歳以上になると利用できるサービス
サービスの認知度で、「知っている」という割合が最も高かったのは、「就労継続支援(A型、B型)」で61.8%となっています。次いで「生活介護」の52.6%、「共同生活援助」の47.4%等と続いています。
逆に「知らない」という割合が最も高かったのは、「療養介護」の69.7%となっています。
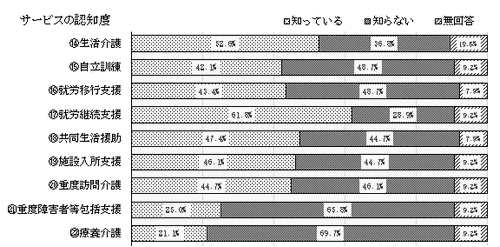
「利用したい」の割合が最も高かったのは、「就労継続支援(A型、B型)」の25.0%となっています。次いで「就労移行支援」の21.1%、「自立訓練」及び「共同生活援助」の同率14.5%等と続いています。
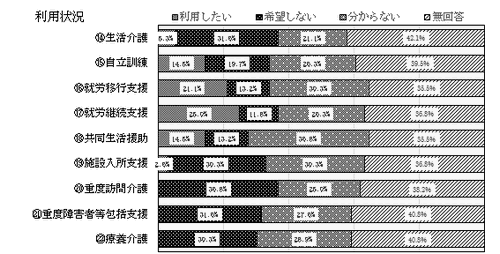
問18 サービスの利用に関して困ったこと
サービスの利用に関して、困っていることの第1位は「サービスに関する情報が少ない」で40.8%なっています。第2位は「市役所での手続きが大変」の38.2%、第3位は「とくにない」の19.7%、第4位は「事業者との利用日等の調整が大変」及び「どこに相談したらいいかわからない」が同率の18.4%等と続いています。
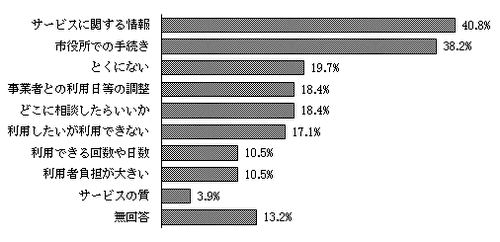
<自由記載> 日常生活における介助や支援について
【 食事について 】
・食事療法をしているが作れる人が両親以外にいない。支援学校へ給食の対応を3年かけてお願いしているが断られた。アレルギー食等は対応しているのにそれ以外は対応できない事に疑問を感じる。
・子へ火や包丁など、どこまでが危なくてこうなるとかの説明が難しい。頭では理解しているようだが、実際は把握できていない様で火傷したことがある。
【 入浴について 】
・身体が大きくなってきて、風呂場が狭いので入浴の手伝いや入浴サービスがあってほしい。
・お風呂などの介助を手伝ってもらいたい。
【 預けられる場所について 】
・土日(兄弟の行事など)に預け先がなく困っている。土・日・祝日に預けられる場所や夜の外出(数時間)の際に預けられる場所、至急の用事などができた時、預けられる場所があると助かる(ショートステイなど)。
・母(自分)が高熱を出した時に、子供を見るのでとてもつらい。実家のお泊りが全くできないので、病欠(不登校)でも預かってくれる場所が欲しい。
【 外出について 】
・親が身体的に外出が出来ずこもりっきりになっているため、外出や学校までの迎えが大変。
・通院や通学、それ以外の外出時に付き添いや介助が必要。
【 その他 】
・認定こども園で日中過ごしているが、言葉が話せないため友達の中に入りにくい。自分の子どもばかりを見られないことが分かり、加配をお願いしたが、できないと役所に言われた。
・交通ルールや注意の仕方など、発達障害のある子にはどのように教えたらいいのか、アドバイスが欲しい。
・発達障害当事者の集まり、語る会の開催や相談できる機会がほしい。
・日常生活動作を学んだり、訓練する療育施設をつくってほしい。
・手伝ってくれる人がいないため、将来的に不安。
<自由記載> ご意見・ご要望
【福祉サービスや事業所等について】
・サービスを利用する時や就学先を決めるタイミングですべての施設の情報を知りたい。年に1~2回、ホールに施設ごとのブースを設けて一度に話が聞ける機会や、各施設の情報が載った冊子があったら欲しい。
・事業所側が人手が足りないのか、定員がいっぱいで利用できないことがある。
・事業所で障害特有のこだわりや、他人の感情を理解できないなどのために起きる問題に適切に対応してもらえない。
・事業所に通っているが、情報交換がなく何をしているか分からない。行かせる意味があるのか分からない。日記などで報告が欲しい。
・土曜日に利用できるサービスがない。利用者が多いから、人手が足りないから、と預かってもらえない。
・日中一時支援事業を利用し助かっているが、利用者が少ない等気軽に頼みづらい。
・言語訓練のできる施設を増やして欲しい。
・障害児入所支援の提供ができる事業所を早急に作ってほしい。沖縄本島に預ける事になると、家族での移住等も考慮しなければならない為、経済的・精神的な負担が計り知れない。
・家族構成や事情によっては、家族の病気などでどうしても一時的にとか、何日間だけなどで短期入所ができると助かる。
・子どもが2人障害児で、周りに協力をお願いしづらい(身体的負担が大きいため)。体が大きくなってきていて毎日、車イスへの乗降等が大変で、精神的にもきつい。
・発達障害の作業療法士、言語聴覚士が少なく、十分な療育が受けられない。
・相談支援員を探すのに時間がかかり、とても不安だった。
・相談支援事業所の相談員の専門的知識や質の向上が必要だと感じる。
・相談支援員の役割がよくわからない。
【教育・学校等について】
・発達障害は目で見て分かりにくい障害のため、まず教育現場(小・中・高・幼稚園・保育園)の先生方に理解していただきたいので、定期的に講習会を開いてほしい。
・加配等を付けてもらうにあたり、子どもの特性を理解し、それに見合った支援員を付けてほしい。
・就職の時期を迎えた子たちは、支援学校に通っていれば学校の支援がある程度受けられるかもしれないが、普通校に通う子は自信を持って希望の就職先を決めることも難しく、自信を失い、悪くすれば二次障害への道に入って行くのではと不安。
・支援学校への看護師配置を望む。
・普通の学校に通っているが、修学旅行や学校外授業の遠足など、長距離歩行を要する時に介護員が必要になりその時だけ要請したいがいつも断られる。市役所に相談したら教育委員会に行ってと言われ、教育委員会に行ったら事例がないので予算がないと断られた。
・障がい福祉課と教育委員会の協力体制等検討してほしい。
【行政等について】
・支給決定までに時間がかかり過ぎ?もっと早く利用できるようにしてほしい。
・手帳の更新が面倒。手帳取得(更新)の際、診断書の提出で病院に行くので、病院から手続き可能にしてほしい。
・サービスを利用する前の相談窓口がちゃんとわかりやすい状態であってほしい。
・育てにくさを感じる頃や、生まれてきた子に「障害がある」と言われて途方にくれる頃、悩みを聞きながら支援が受けられることを一緒に考えてくれる窓口がほしい。
・様々な制度やサービスの窓口がその種類によってバラバラなので、せめてガイドしてくれる窓口を1つ作ってくれたら有り難い。
・事業所を利用するにも手続きが多く、障がい福祉課という所での受付なのでどうしても一歩踏み出しにくい。
・福祉に関するサービス等は、できれば学校を通して、もしくは、見やすく、新しい情報を市のHPに掲載して欲しい(市のHPは、見づらく、古い情報もあったりと非常に不便)。
【その他】
・自閉症スペクトラムの娘がおり、当事者の会(自閉の会)などはないのか?自分ではなかなか探せない (日々の生活で保護者は手いっぱいだったりします)。もっと学童等に声かけ、パンフ等の配布、紹介などできないか?健常児のママとも交流あるが、悩みの内容が違うので、相談などまず出来ない。
・高校生になり、医療行為である導尿を自分でできるようになったが、小学校高学年ぐらいまでは家族以外のサポートが必須だった。そのサポート先を探すまでは本当に大変だった。医療ケアを必要としている家族への、積極的な情報提供を要望したい。
・3年に1度、東京の病院に通院しているが、これと言っての支援金が無いため、自己負担が大変。小さい時は手当はあったが、3歳以降ないので、何か少しでもあると金銭的にも助かる。
・まだ未就学児なので、これからいろいろと悩んだり困ったりすると思う。今思うことは、療育を受ける場がないこと。発達に関して、専門家の指導を受ける機会が少なく、選択肢もない。療育相談も、八重山病院で定期的に受けられるようになればいいと思う。
・子どもの多い家庭、母子・父子家庭、障がい児のいる家庭の家庭訪問をして話を聞いてほしい。肉体的、精神的、金銭面で困っている人がいっぱいいると思う。








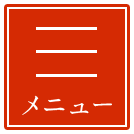
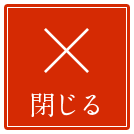
更新日:2020年08月27日