資料編
資料編
1 第4次石垣市障がい者福祉計画・第4期石垣市障害福祉計画策定の経緯
| 年月日 | 内容 |
|---|---|
| 平成26年7月16日 | 第1回調整会議 |
| 平成26年8月26日 | 第2回調整会議 |
| 平成26年9月19日 | 第3回調整会議 |
| 平成26年9月29日 | 第4回調整会議 |
| 平成26年9月30日 | 策定委員会委嘱状交付式・市長より諮問・第1回策定委員会 |
| 平成26年10月29日 ~11月30日 |
アンケート調査 |
| 平成26年11月14日 | 第5回調整会議 |
| 平成26年12月12日 | 第1回ヒアリング(相談支援事業所) |
| 平成26年12月13日 | 第1回ワークショップ(八重山身体障害者福祉協会(1)) |
| 第2回ワークショップ(障がい者の親の会(1)) | |
| 平成26年12月19日 | 第2回ヒアリング(障がい児親の会等) |
| 第3回ワークショップ(知的・精神障がいの皆さん) | |
| 第3回ヒアリング(福祉サービス提供事業所) | |
| 平成26年12月20日 | 第4回ワークショップ(障がい者の親の会(2)) |
| 第5回ワークショップ(八重山身体障害者福祉協会(2)) | |
| 第6回ワークショップ(聴覚障がい者の皆さん) | |
| 平成26年12月24日 | 第2回策定委員会 |
| 平成27年1月16日 | 第4回ヒアリング(介助を要する子の親の会) |
| 第5回ヒアリング(難病を抱える方、支える方の皆さん) | |
| 平成27年2月8日 | 計画(素案)検討会議 |
| 平成27年2月12日 ~2月18日 |
計画(素案)関係各課等へ照会 |
| 平成27年2月12日 | 第6回調整会議 |
| 平成27年2月13日 | 第3回策定委員会 |
| 平成27年2月20日 | 第7回調整会議 第4回策定委員会 |
| 平成27年2月25日 ~3月24日 |
パブリックコメント実施 |
| 平成27年3月25日 | 計画(成案)検討会議 |
| 平成27年3月26日 | 市長へ答申 |
| 平成27年3月27日 | 庁議へ付議(『計画』決定) |
| 平成27年3月17日 ~3月27日 |
愛称募集 |
| 平成27年3月30日 | 愛称選考委員会(『愛称』決定) |
2 第4次石垣市障がい者福祉計画及び第4期石垣市障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成26年9月2日
平成26年石垣市告示第176号
(設置)
第1条 第4次石垣市障がい者福祉計画及び第4期石垣市障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、第4次石垣市障がい者福祉計画・第4期石垣市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画策定に関する施策の意見集約及び調査研究、企画立案に関すること。
(2) その他、計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のなかから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 障がい者
(3) 障がい者の福祉に関する事業に従事する者
(4) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定の日までとする。
2 任期中において、委員の交代があった場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。
(支援者の同席)
第7条 委員長は、委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者が障がい者である場合に、当該委員及び出席者の障害特性により必要があると認めるときは、当該委員の介助、発言の補助その他必要な支援を行う支援者を会議に同席させることができるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉部障がい福祉課において処理する。
(設置期間)
第9条 委員会の設置期間は、設置の日から計画が策定された日までとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、第9条に規定する委員会の設置期間の満了の日限り、その効力を失う。
3 第4次石垣市障がい者福祉計画・第4期石垣市障害福祉計画策定委員会名簿
| No. | 氏 名 | 所 属 (役職等) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小倉隆一 | 社会福祉士 | |
| 2 | 俵崇記 | 精神科医師 | |
| 3 | 島袋正都 | 八重山福祉保健所(福祉総括) | |
| 4 | 長浜末子 | 八重山福祉保健所(保健総括) | |
| 5 | 玻名城安教 | 八重山特別支援学校(校長) | |
| 6 | 比嘉玉子 | 八重山身体障害者福祉協会(会長) | |
| 7 | 大濵守哲 | 八重山精神療養者家族会「やらぶの会」(代表) | |
| 8 | 仲松芳子 | 八重山地区手をつなぐ育成会(代表) | |
| 9 | 長谷部弘美 | 障がい児親の会(代表) | |
| 10 | 伊良部義一 | 石垣市社会福祉協議会(事務局長) | |
| 11 | 東宇里永清 | 石垣市民生委員児童委員協議会(会長) | 委員長 |
| 12 | 津嘉山航 | 沖縄県相談支援体制整備事業アドバイザー | 副委員長 |
| 13 | 前津榮要 | 社会福祉法人 若夏会 (施設長) | |
| 14 | 島袋喜代美 | 社会福祉法人 わしの里 (施設長) | |
| 15 | 真鍋幸子 | 社会福祉法人 綾羽会 (施設長) | |
| 16 | 宇根眞利子 | 特定非営利活動法人 ちゅらネット(代表) | |
| 17 | 矢崎真一 | 合同会社 ファーストハンドコミュニケーション(代表) | |
| 18 | 知念修 | 福祉部長 | |
| 19 | 長嶺康茂 | 市民保健部長 | |
| 20 | 成底啓昌 | 教育部長 |
4 第4次石垣市障がい者福祉計画・第4期石垣市障害福祉計画アンケート調査の概要
1) アンケートの実施概要
調査の対象は、本市に在住する65歳未満の障害者手帳所持者等の1,280人が調査対象となっています。
2) 調査対象地域
石垣市全域
3) 調査の期間
平成26年10月下旬~平成26年11月末日
4) 調査票配布回収方法
対象者に対し、郵送による配布・回収を実施しました。調査票の回収に際しては、サービス提供事業者や各種関係団体等への協力依頼及び調査対象者へ直接電話による調査票の返信勧奨を行いました。
5) 調査票の回収状況
| 配布数 | 回収数 | 有効回答数 | 実質回収率 | |
|---|---|---|---|---|
| 調査票回収状況 | 1,280 | 565 | 552 | 43.1% |
2 調査結果の概要
(1) 調査票回答者
アンケートの記入者は、「本人」が59.8%で最も高くなっています。
次いで「本人・家族等」の25.9%、「家族以外の介助者や支援者」の4.9%となっております。
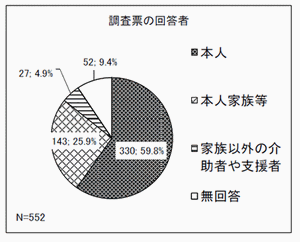
(2) 年 齢(平成26年10月1日)現在
調査対象者の年齢層は、「50~59歳」が28.1%で最も高くなっています。
次いで「60歳以上」の21.7%、「40~49歳」の19.2%、「30~39歳」の11.4%、「20~29歳」の6.7%等と続いています。
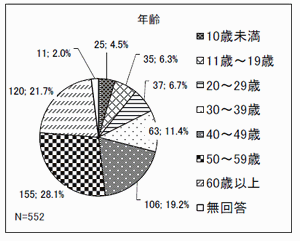
(3) 同居家族
一緒に暮らしている同居家族は「父母・祖父母・兄弟」が42.8%で第1位となっています。
第2位は「いない(一人で暮らしている)」の26.8%、第3位は「配偶者(夫または妻)」の25.7%、第4位は「子ども」の14.5%、第5位は「その他」の4.3%となっています。
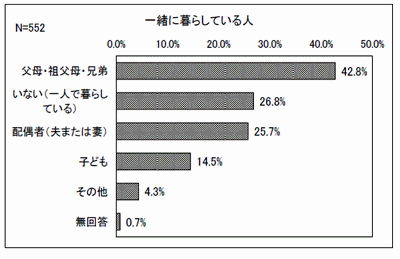
(4) 身体障害者手帳の状況
1)手帳の所持及び等級
障害者手帳の所持者数は、377人となっています。
記載されている等級は「1級」が37.4%で最も高くなっています。
次いで「2級」の31.0%となっており、重度の等級である「1級」、「2級」の合計割合は68.4%となっています。
以下、「3級」の11.7%、「4級」の10.6%、「5級」の5.0%、「6級」の4.2%となっています。
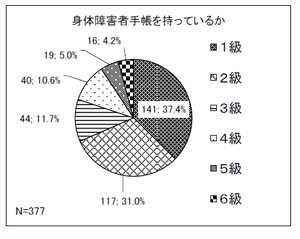
2)おもな障害の種類(限定質問)
障害者手帳に記載されている、おもな障害の種類は、「内部障害」が30.0%で最も高くなっています。
次いで「肢体不自由(下肢)」の22.5%、「肢体不自由(上肢)」の9.5%、「肢体不自由(体幹)」の9.3%、「聴覚障害」の8.5%、「視覚障害」の5.8%、「音声・言語・そしゃく機能障害」の4.2%となっています。
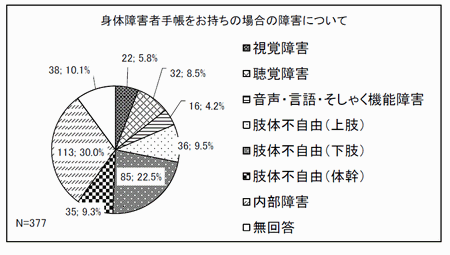
(5) 療育手帳所持及び判定
療育手帳の所持者は140人となっています。
記載されている等級は「B判定」の76.4%、「A判定」の23.6%となっています。
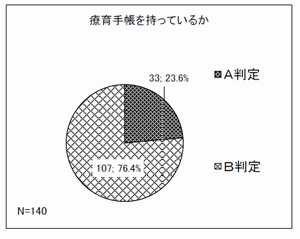
(6) 精神障害者保健福祉手帳所持及び等級
精神障害者福祉手帳所持者数は109人となっています。
記載されている等級は「2級」の59.6%、「1級」の26.6%、「3級」の13.8%となっています。
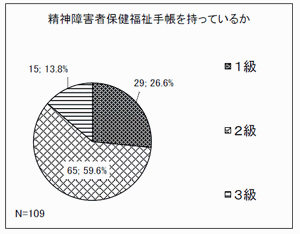
(7) 難病(特定疾患)認定
難病(特定疾患)の認定は「受けていない」が81.2%、「受けている」が8.5%となっています。
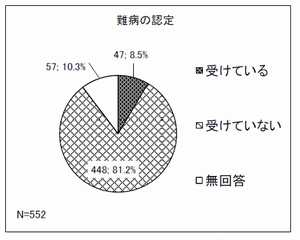
(8) 日常生活で介助が必要なこと
日常生活で介助が必要かについては、「ひとりでできる」割合が最も高い動作は「家の中の移動」で84.4%となっています。
次いで「食事」83.9%、「トイレ」82.8%、「衣服の着脱」79.0%、「入浴」76.8%等と続いています。一方、「一部介助が必要」、「全部介助が必要」の割合が高い動作、項目は、「お金の管理」で35.7%となっています。次いで「薬の管理」の31.2%、「外出」の29.2%、「家族以外の人との意志疎通」23.4%、「身だしなみ」の20.7%等と続いています。
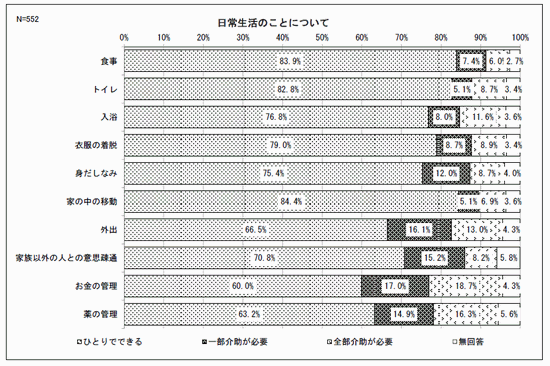
(9) 主に介助をしている方(限定質問)
主に介助をしている方割合の第1位は「父母・祖父母・兄弟」の50.2%なっています。
第2位は「ホームヘルパーや施設の職員」の28.0%、第3位は「配偶者(夫または妻)」の13.3%、第4位は「子ども」の5.5%、第5位は「その他の人(ボランティア等)」の3.0%となっています。
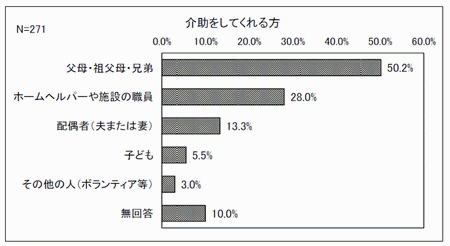
(10) 暮らしについて
暮らしについては、「家族と暮らしている」が65.6%で最も高くなっています。
次いで「一人で暮らしている」の20.1%、「福祉施設(障害者支援施設、高齢者支援施設)で暮らしている」の5.6%、「その他」の2.0%、「グループホームで暮らしている」の1.1%となっています。
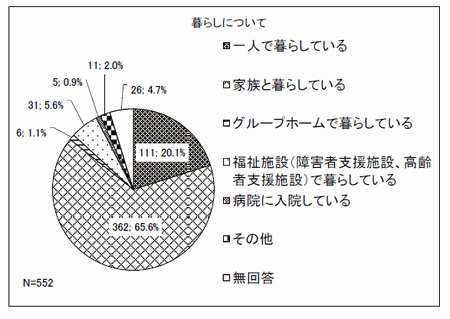
(11) 生活について(限定質問)
生活については、「今のまま生活したい」が61.1%で最も高くなっています。
次いで、「家族と一緒に生活したい」の16.7%、「グループホームなどを利用したい」の5.6%、「一般の住宅で独り暮らしをしたい」及び「その他」が同率の2.8%となっています。
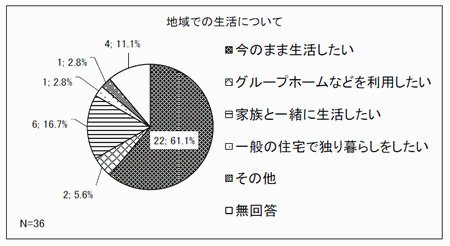
(12) 生活するために必要な支援
生活するために必要な支援は、「経済的な負担の軽減」が52.9%で最も高くなっています。
次いで「障がい者に適した住居の確保」の36.8%、「相談対応等の充実」の35.1%、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」の34.4%、「地域住民等の理解」の28.3%等と続いています。
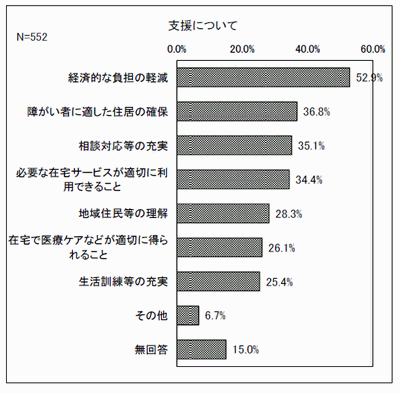
(13) 外出の時困ること(限定質問)
外出の時に困ることの第1位は、「困った時にどうすればいいのか心配」で24.6%となっています。
第2位は「外出にお金がかかる」の23.2%、第3位は「外出先の建物の設備が不便(通路、トイレ、エレベーターなど)」の18.0%、第4位は「発作など突然の身体の変化が心配」の16.2%、第5位は「公共交通機関が少ない、又はない」の16.0%等と続いています。
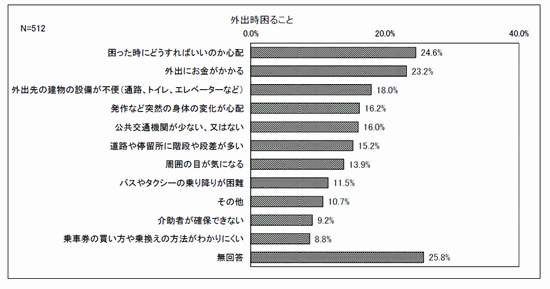
(14) 平日の過ごし方
平日の過ごし方の第1位は、「会社勤めや、自営業、家業などで収入を得て仕事をしている」で25.4%となっています。
第2位は「自宅で過ごしている」の24.8%、第3位は「福祉施設、作業所等に通っている(就労継続支援A型も含む」の14.5%、第4位は「専業主婦(主夫)をしている」の5.8%、第5位は「入所している施設や病院等で過ごしている」の5.3%等と続いています。
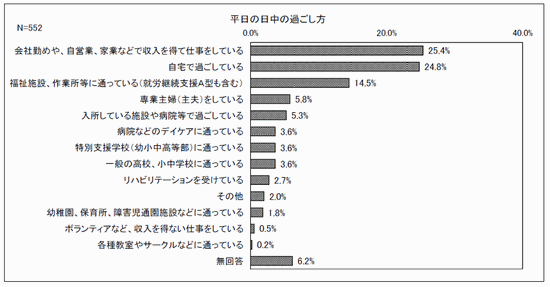
(15) 勤務形態について(限定質問)
勤務形態は、「パート・アルバイト等の非常勤職員、派遣職員」が40.7%で最も高くなっています。次いで「正職員で他の職員と勤務条件等に違いはない」の25.0%、「自営業、農林水産業など」の15.7%、「正職員で短時間勤務などの障がい者配慮がある」の12.1%「その他」の3.6%となっています。
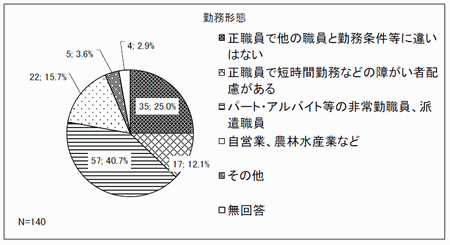
(16) 就労支援について(限定質問)
平日の過ごし方の第1位は、「職場の上司や同僚に障害の理解があること」で43.3%なっています。
第2位は「会社(経営者)の障がい者理解」の39.1%、第3位は「短時間勤務や勤務日数等の配慮」の34.4%、第4位は「通勤手段の確保」の31.3%、第5位は「仕事についての職場外での相談対応、支援」の29.5%等と続いています。
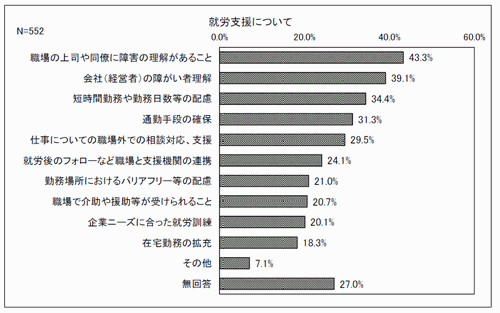
(17) 障害支援(程度)区分
障害支援(程度)区分ついては、「わからない」が37.3%で最も高くなっています。
次いで「受けていない」の29.7%、「区分2」の3.4%、「区分6」の3.3%、「区分4」の2.7%、「区分3」及び「区分5」が同率の2.2%、「区分1」1.4%となっています。
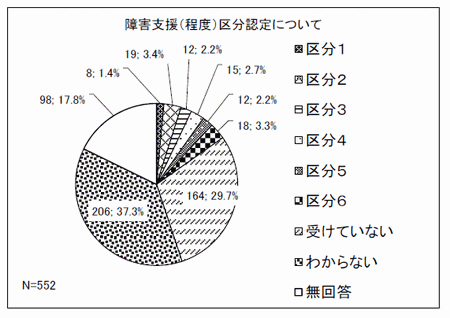
(18) 利用できるサービス
利用できるサービスは、「知らない」が67.9%、「知っている」の15.4%となっています。
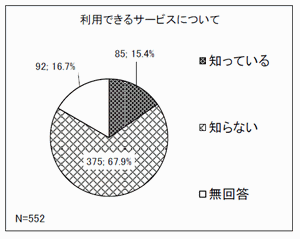
(19) 悩みや困った時の相談先
悩みや困った時の相談先の第1位は「家族や親せき」で66.3%なっています。第2位は「友人・知人」の32.1%、第3位は「かかりつけの医師や看護師」の25.2%、第4位は「相談支援事業所などの相談窓口」の16.1%、第5位は「施設の指導員など」の12.1%等と続いています。
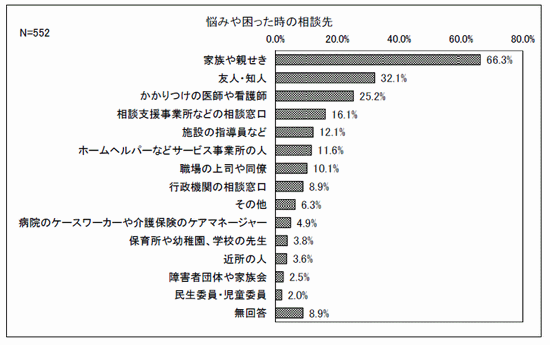
(20) 福祉サービスに関する情報の入手先
悩みや困った時の相談先の第1位は、「本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース」で35.0%なっています。
第2位は「家族や親せき、友人・知人」の33.0%、第3位は「サービス事業所の人や施設職員」の21.4%、第4位は「かかりつけの医師や看護師」の20.1%、第5位は「行政機関の広報誌」の17.0%等と続いています。
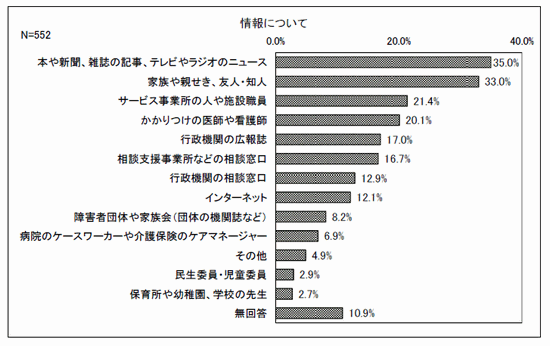
(21) 差別や嫌な思い
差別や嫌な思いをしたことがあるかについては、「ない」が34.1%で最も高くなっています。
次いで「ある」の31.7%、「少しある」の25.5%となっており、「ある」の合計割合は57.2%と全体の約6割を占める状況となっています。
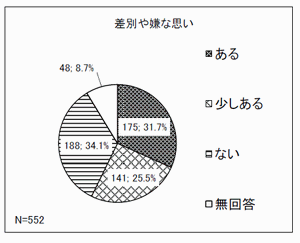
(22) 成年後見制度について
成年後見人制度ついては、「名前も内容も知らない」が54.5%で最も高くなっています。
次いで「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」の19.9%、「名前も内容も知っている」の25.5%となっています。
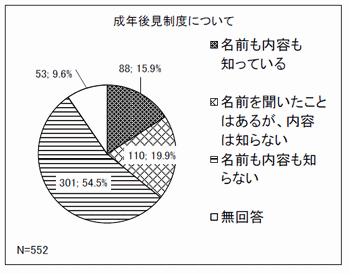
(23) 知っている内容について
1)石垣市障がい者虐待防止センター
石垣市障がい者虐待防止センターついては、「わからない」が73.4%、「知っている」が15.4%となっています。
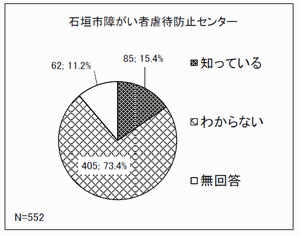
2)石垣市障がい者基幹相談支援センター
石垣市障がい者基幹相談支援センターについては、「わからない」が71.4%、「知っている」が16.5%となっています。
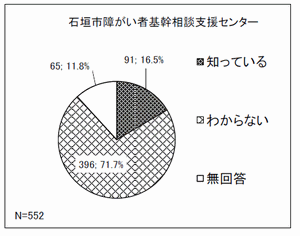
3)沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例
(共生社会条例)
沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例について知っていますかについては、「わからない」が75.5%、「知っている」が12.3%となっています。
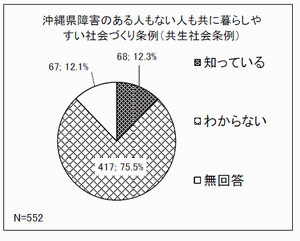
(24) 災害時の避難
火事や地震等の災害時に一人で避難できますかについては、「できる」が42.4%で最も多くなっています。
次いで「できない」の30.4%、「わからない」の21.6%となっています。
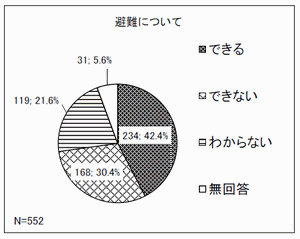
(25) 助けてくれる人について
家族が不在の場合や一人暮らしの場合、近所にあなたを助けてくれる人はいますかについては、「いない」が34.6%で最も多くなっています。
次いで「わからない」の31.0%、「いる」が26.6%となっています。
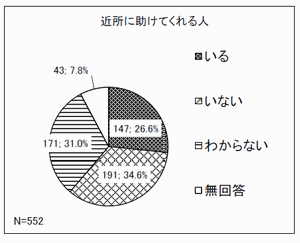
(26) 災害が起きた時に困ること
火事や地震等の災害が起きた場合に困ることについては、「投薬や治療が受けられない」が46.6%で第1位となっています。
第2位は「避難場所の設備(トイレ等)や生活環境が不安」で40.6%、第3位は「安全なところまで、迅速に避難することができない」の39.7%、第4位は「被害状況、避難場所などの情報が入手できない」の26.4%、第5位は「周囲とコミュニケーションがとれない」の25.4%等と続いています。
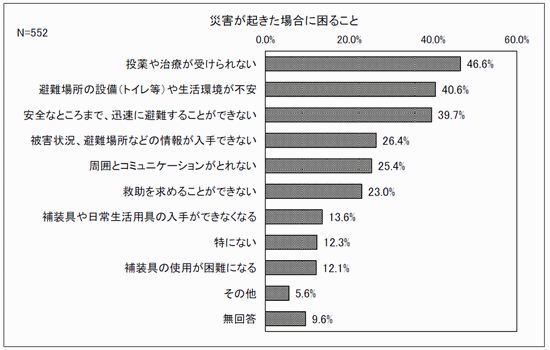
(27) 地域社会での活動
地域での活動に参加していますかについては、「参加しない」が64.1%で最も多くなっています。
次いで「時々参加する」の24.3%、「よく参加する」の6.7%となっています。
頻度に関わらず「参加する」の割合は31.0%となっています。
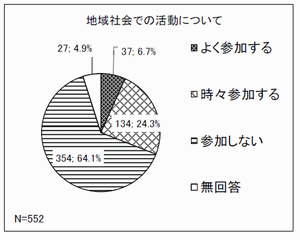
(28) 障がい者に対する理解
地域や住民の障がい者に対する理解は深まってきたと思いますかについては、「わからない」が38.4%で最も多くなっています。
次いで「少し理解されてきた」の18.8%、「あまり理解されていない」の17.2%、「理解されていない」の10.9%、「理解されてきた」の9.6%となっています。
理解の状況に関わらず、「理解されてきた」とする割合は28.4%、「理解されていない」とする割合が28.1%となっています。
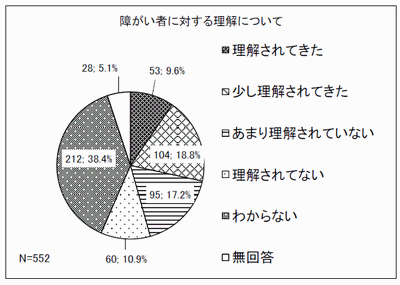
5 「第4次石垣市障がい者福祉計画・第4期石垣市障害福祉計画」策定にかかわるワークショップの概要
障がいのある方や、身体・知的障がい者の親の会の皆さまに、石垣市の障がい者の福祉について、問題点・課題等、そして、それを解決するためのアイディア等を出し合っていただきました。
下表は、その概要であります。 詳細については、第4次石垣市障がい者福祉計画中【市民の声】に抜粋して載せてあります。
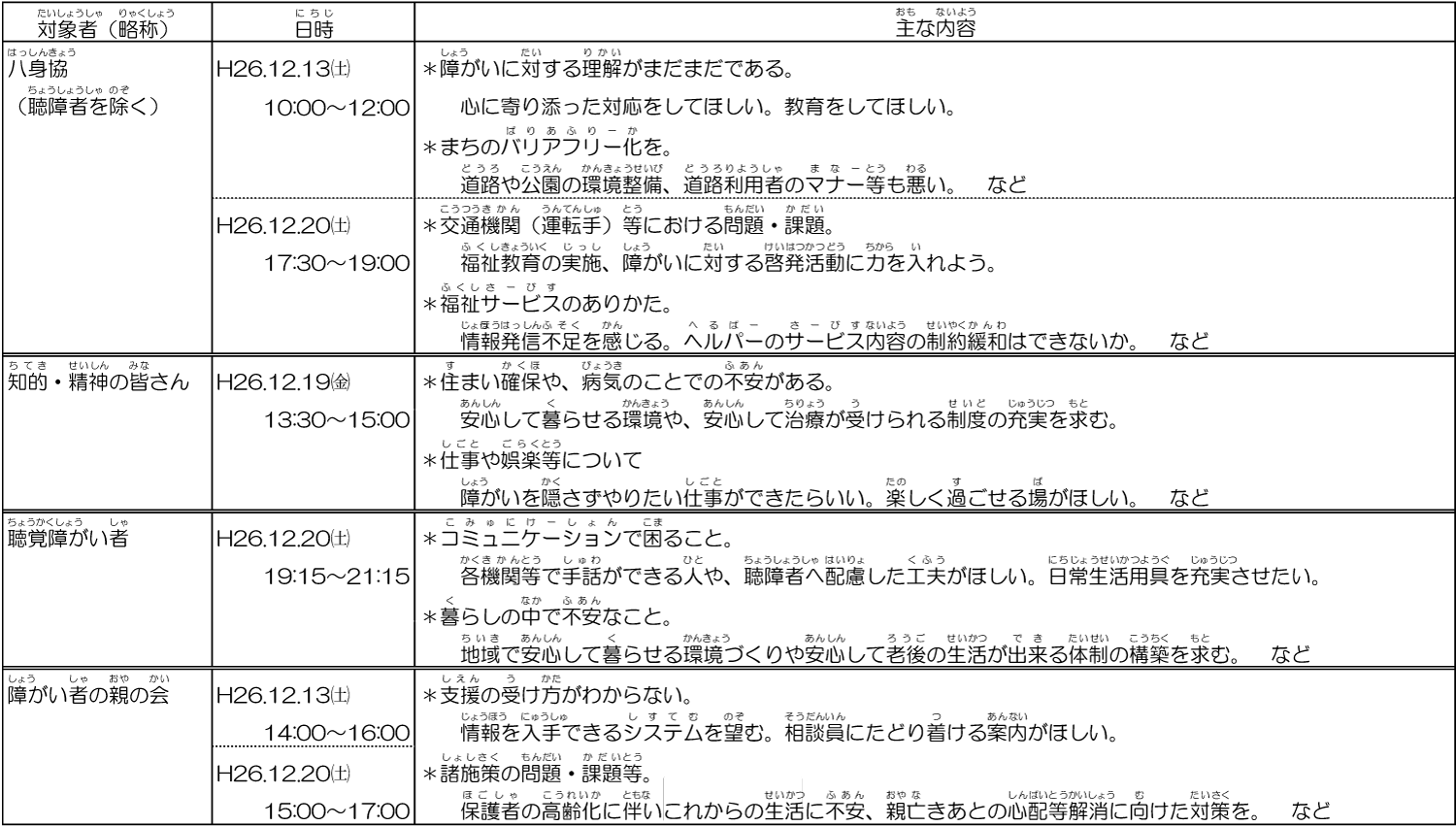
6 「第4次石垣市障がい者福祉計画・第4期石垣市障害福祉計画」策定にかかわるヒアリングの概要
相談事業所、福祉サービス事業所や親の会、難病患者の皆さま等へ、石垣市の障がい者福祉についてのヒアリングをさせていただきました。
貴重なご意見、ご提言をたくさん頂戴しました。
下表は、その概要であります。 詳細については、第4次石垣市障がい者福祉計画中【市民の声】に抜粋して載せてあります。
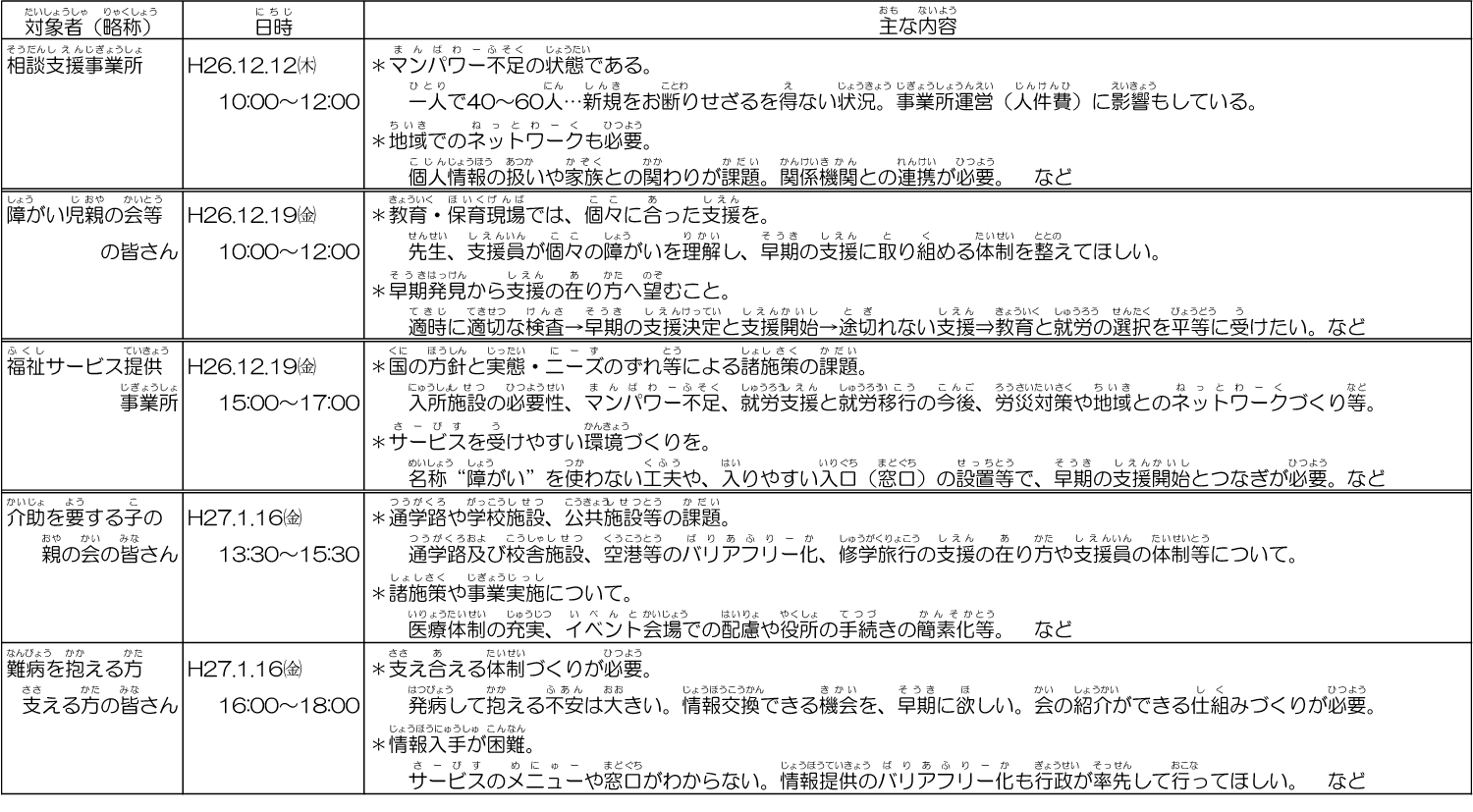
7 用語の解説
【あ行】
□アスペルガー症候群
自閉症のうち、知的障害を伴わず、比較的良好な言語的コミュニケーションがとれます。
□NPO
正式には「非営利組織」といい、狭い範囲では市民活動団体を指すこともあります。医療、福祉、環境、文化、芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教育等のあらゆる分野の民間の営利を目的としない組織です。
□LD
発達障害〔LD〕の知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す発達障害のことです。
□ADHD
注意欠陥多動性障害のことです。注意力・衝動性・多動性を自分でコントロールできない脳神経学的な疾患と言われています。
【か行】
□権利擁護
自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障がい者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことです。
□高機能自閉症
知的障害を伴わない自閉症のことをいいます。発達障害の一つであり、知能指数が高いが、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわるといった自閉症の特徴を持ちます。
【さ行】
□災害時要援護者
高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、傷病者、日本語が不自由な外国人といった災害時に自力で避難することが困難な人のことです。
□社会資源
福祉ニーズを充足するさまざまな物資や人材、制度、技能の総称として用い
ます。
□社会福祉協議会
社会福祉法の規定に基づき組織される地域福祉の推進を目的とする団体で、さまざまな福祉サービスや相談、ボランティア活動や市民活動の支援、共同募金など地域の福祉の向上に取り組んでいます。
□社会福祉士
社会福祉に関する専門的な知識と技術をもって、身体上、または精神上の障害があったり、もしくは環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があったりする人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行います。また、医療関係者をはじめとした福祉サービス関係者等と連携し、これらとの連絡・調整、援助を行うソーシャルワーカーです。
□障害支援(程度)区分認定
市町村が障害福祉サービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分です。
□障害者週間
障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
□自立支援協議会
障がい者の地域における自立生活を支援していくため、関係機関・団体、障がい者・その家族、障害福祉サービス事業者や医療・教育・雇用を含めた関係者が、地域の課題を共有し、地域の支援体制の整備について協議を行う場で、地方公共団体が単独または共同により設置されるものです。
□成年後見制度
認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、意思能力がない、又は、判断能力が不十分な成年者のために、金銭や身の回りの管理や保護に関する契約等の法律行為全般を行うための制度です。
□相談支援員
障がい者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス利用計画を作成する者をいいます。
【た行】
□地域活動支援センター
障がい者を対象とする通所施設の一つです。地域の実情に応じ、創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与し、障がい者の自立した地域生活を支援する場です。
□特別支援教育支援員
障害の種類や程度に応じ特別の場で指導を行っていた特殊教育を転換し、通常学級に在籍する学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等の児童・生徒も含め、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
【な行】
□ノーマライゼーション
「社会的に不利を負うと考えられる人が、あるがままの姿で他の人と同等の権利を享受できるようにする」ことをめざす考え方です。
【は行】
□バリアフリー
もともとは障がいのある人が生活していくうえで、妨げとなる段差等の物理的な障壁(バリア)をなくすことを意味しています。現在では物理的な障壁に限らず、制度や心理的な障壁を含め、あらゆる障壁を取り除く意味で用いられています。
□PDCAサイクル
計画(plan)→実行(do)→評価(check)→改善(act)という4段階の活動を繰り返し行う事で、継続的にプロセスを改善していく手法です。
【や行】
□ユニバーサルデザイン
障がい者、高齢者、健常者の区別なしに、すべての人が使いやすいように製品、建物、環境などをデザインすることです。
【わ行】
□ワークショップ
参加者が、ある目的に対し、相互の意見を取り入れながら課題の明確化や解決方法策の提示などを具体化しようとする取り組みのことです。








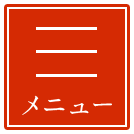
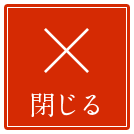
更新日:2020年03月02日