幼児教育・保育の無償化について
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。幼稚園や保育園(所)、認定こども園などを利用する3~5歳の子どもと、0~2歳の住民税非課税世帯の子どもの施設等利用料が無償となります。
なお、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない認可外保育施設は、保育の無償化の対象外です(令和6年10月以降)。
無償化の対象となる子ども
●3~5歳の子ども
●住民税非課税世帯の0~2歳の子ども
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
(3歳児クラス~5歳児クラス)です。
※幼稚園・認定こども園(教育認定)については、入園できる時期に合わせて、
満3歳児から無償化されます。
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(R7年8月) (PDFファイル: 385.0KB)
沖縄県子育て支援課(外部リンク。別ウインドウで開きます)認可外保育施設の個別情報
【子育てのための施設等利用給付認定の申請・変更申請方法】
申請にあたっては、必ず下記パンフレットをご確認いただき、必要書類等のご確認をお願いいたします。
幼児教育・保育の無償化のご案内パンフレット(PDFファイル:861.4KB)
[提出先]
石垣市子育て支援課(57~60番窓口)
(電話番号:0980-82-1704)
※書類が揃っていない場合や記入漏れがある場合は、受理できません。
[提出書類]
★新1号(教育部分利用)・新2号(預かり保育利用)共通申請書
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月までに施設利用を開始する方)
●令和7年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例)【PDF(PDFファイル:800.8KB)
●令和7年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例)【Excel】(Excelファイル:90.2KB)
令和8年度(令和8年4月以降に施設利用を開始する方)
●令和8年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例)【PDF】(PDFファイル:1.6MB)
●令和8年度 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(指定様式・記入例)【Excel】(Excelファイル:88KB)
★新2号・新3号認定には下記の保育を必要とする要件書類(指定様式)が必要です。
※新3号認定は下記の要件及び非課税世帯が対象です。
就労証明書(指定様式)【PDF】 (PDFファイル: 5.3MB)
就労証明書(指定様式)【Excel】 (Excelファイル: 84.8KB)
求職活動申立書(指定様式) (PDFファイル: 138.1KB)
※認定を受けた後、住所の変更や連絡先、保育の必要性(就労等)が変更になる場合は
下記の施設等利用給付認定変更届の提出が必要です。
施設等利用給付認定変更届(指定様式) (PDFファイル: 138.9KB)
★現況確認について★
施設等利用給付認定(幼児教育・保育の無償化)を受けている場合は、毎年現況確認(「保育の必要性」の有無の確認)が必要となります。
現況確認の対象者は毎年4月1日以前の認定者となっております。例年8月頃に現況対象者へ通知しております。通知が届いた方は内容をご確認のうえ、子育て支援課窓口までお越しください。
現況確認が未確認となる場合、施設等利用給付費をお支払いすることが出来ませんので、ご注意ください。








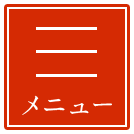
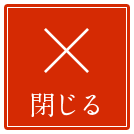
更新日:2025年10月30日